本回から少し、聞いたことあるけれど、詳しく分からないであろう、省エネ給湯について解説していきます。
是非、参考に!!
エコウィル
内燃式ガスエンジンによる世界初・世界最小の家庭用ガスコージェネレーションシステム。
構成・仕様
ガスエンジン、発電機、インバーターなどからなる「ガスエンジン発電ユニット」、と、
貯湯タンク、補助熱原機、熱交換器やポンプなどからなる「排熱利用給湯暖房ユニット」、の、二つで構成。
都市ガスまたはLPガスを燃料として、ガスエンジンを駆動し、発電機を回すことによって発電。
発電出力1kWの小出力一定運転で、住宅内の電力負荷が1kW未満のときに発電運転する場合は、電気ヒーターを用いて余剰電力を熱に交換し、排熱として回収する。
発電と同時に発生する熱は、温水として回収され、排熱熱交換器を介して排熱利用給湯暖房ユニット内の貯湯タンクに貯められ、給湯やお湯はりに使用される。
また、温水暖房使用時にはエンジンの排熱を直接熱交換して効率よく暖房に利用する回路構成となっている。
貯湯タンクのお湯がなくなった場合や、排熱量だけで熱需要が賄えない場合は、補助熱原機を運転する。
省エネルギー性・環境性
発電効率 22.5%、排熱回収効率 63%、総合効率 85.5%。
一次エネルギー消費量 21%削減、CO2排出量 32%削減。
参考文献:建築技術2010.1号
木曜日, 6月 24, 2010
金沢のアーティスト1
劇団アンゲルス
今回からは金沢のアーティストもご紹介します。最初は「舞台芸術」。
私が演劇に興味を持ち出した理由は、古代・中世では建築家が劇場を設計することはかなり栄誉なことだったと言う事を知ったからでした。
現代で考えても技術的には大空間を造る構造的技術・音をコントロールするための音響技術・舞台機構を造る機械的技術・大空間の室内環境をコントロールする空調技術・災害時の集団の安全の確保、これらは他のビルディングタイプでは旧来の技術で出来ます。劇場は全てを最新技術を用いて造らなければなりません。そして人が集まる事や、数百人・数千人が同じ事象に同時に注視する空間を考えること・芸術に耐えうる建築であること等々、統合すべき事象の多さと重要度は他の建物を圧倒します。
この事を知る挑戦心のかたまりのような建築家たちは劇場やコンサートホールの設計への挑戦権獲得に血眼になります。
もひとつの理由は「光」です照明の演出だけで様々な場面が創り出されます。同じ限定された舞台の上に無限の空間が創り出せる事に、我々建築家の造る空間の窮屈さを破るきっかけがあるような気がします。
少し前の時代ハコモノと揶揄された公共の劇場やコンサートホールが沢山造られましたが、地域や社会が成熟すると劇場を欲するのは古代ローマから変わらぬ現象なのではと思えます。
劇団アンゲルスは演出家岡井直道さんが率いる金沢を拠点とする劇団です。東京演劇アンサンブルで演出家をされていた岡井さんが地元のアマと各地のプロの混成で演劇活動をしています。
恥ずかしながら「劇場」には関心があっても「演劇」なぞさっぱりわかりません。岡井さんの存在もしらず何か些細なきっかけで金沢芸術村へ「十二夜」を見に行きました。フーム、シェークスピア!…いなかの劇団がなにか?っつう程度の適当さで足を運びましたが、
ところがどっこい興奮して帰ってきました。
なにがって?……それはよくわかりません、なんせ私に知性を要求してくるようでした。なぜだかこんな知的なもんが金沢にあるんかということに感激したということなんでしょうか。
それとシロート目ながら役者さんにもびっくりしました。こんな迫力ある人が田舎の劇団員?と思いきや月原豊さんや下条世津子さんは東京演劇アンサンブルの俳優だったそうで本物のプロっつうことでした。その人たちは貧乏覚悟で岡井さんと金沢に来たというのに2度びっくり。以前東京で劇団関係の設計をしたときに聞いたのは、地方の時代とかいっても、特に演劇は地方ではだめだというのは定説と聞いたことがあるような。
「子供のためのキントテアター 道化師たち」を見たときも、いくつもの話が前後がややこしくこんな難解なの子供わかんのかなー?と横を向いたら娘がはなぢを出していました。やっぱり子供は理解しなくても感じちゃうのかと思わされました。
なんか気が付くとモルドバの演劇祭に出てきたとか、金沢演劇祭などを立ち上げたり、自らマスターをするカフェシアターでいろんなパフォーマーを出演させたり。細い見かけからは信じられないパワフルさです。
そういえば4年前や8年前のワールドカップ観戦会なんかもしてたけど、今日はやってないのかな?
http://www.angelus-t.com/
http://www.theater-angelus.com/intro.html

にほんブログ村
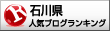
今回からは金沢のアーティストもご紹介します。最初は「舞台芸術」。
私が演劇に興味を持ち出した理由は、古代・中世では建築家が劇場を設計することはかなり栄誉なことだったと言う事を知ったからでした。
現代で考えても技術的には大空間を造る構造的技術・音をコントロールするための音響技術・舞台機構を造る機械的技術・大空間の室内環境をコントロールする空調技術・災害時の集団の安全の確保、これらは他のビルディングタイプでは旧来の技術で出来ます。劇場は全てを最新技術を用いて造らなければなりません。そして人が集まる事や、数百人・数千人が同じ事象に同時に注視する空間を考えること・芸術に耐えうる建築であること等々、統合すべき事象の多さと重要度は他の建物を圧倒します。
この事を知る挑戦心のかたまりのような建築家たちは劇場やコンサートホールの設計への挑戦権獲得に血眼になります。
もひとつの理由は「光」です照明の演出だけで様々な場面が創り出されます。同じ限定された舞台の上に無限の空間が創り出せる事に、我々建築家の造る空間の窮屈さを破るきっかけがあるような気がします。
少し前の時代ハコモノと揶揄された公共の劇場やコンサートホールが沢山造られましたが、地域や社会が成熟すると劇場を欲するのは古代ローマから変わらぬ現象なのではと思えます。
劇団アンゲルスは演出家岡井直道さんが率いる金沢を拠点とする劇団です。東京演劇アンサンブルで演出家をされていた岡井さんが地元のアマと各地のプロの混成で演劇活動をしています。
恥ずかしながら「劇場」には関心があっても「演劇」なぞさっぱりわかりません。岡井さんの存在もしらず何か些細なきっかけで金沢芸術村へ「十二夜」を見に行きました。フーム、シェークスピア!…いなかの劇団がなにか?っつう程度の適当さで足を運びましたが、
ところがどっこい興奮して帰ってきました。
なにがって?……それはよくわかりません、なんせ私に知性を要求してくるようでした。なぜだかこんな知的なもんが金沢にあるんかということに感激したということなんでしょうか。
それとシロート目ながら役者さんにもびっくりしました。こんな迫力ある人が田舎の劇団員?と思いきや月原豊さんや下条世津子さんは東京演劇アンサンブルの俳優だったそうで本物のプロっつうことでした。その人たちは貧乏覚悟で岡井さんと金沢に来たというのに2度びっくり。以前東京で劇団関係の設計をしたときに聞いたのは、地方の時代とかいっても、特に演劇は地方ではだめだというのは定説と聞いたことがあるような。
「子供のためのキントテアター 道化師たち」を見たときも、いくつもの話が前後がややこしくこんな難解なの子供わかんのかなー?と横を向いたら娘がはなぢを出していました。やっぱり子供は理解しなくても感じちゃうのかと思わされました。
なんか気が付くとモルドバの演劇祭に出てきたとか、金沢演劇祭などを立ち上げたり、自らマスターをするカフェシアターでいろんなパフォーマーを出演させたり。細い見かけからは信じられないパワフルさです。
そういえば4年前や8年前のワールドカップ観戦会なんかもしてたけど、今日はやってないのかな?
http://www.angelus-t.com/
http://www.theater-angelus.com/intro.html
にほんブログ村
水曜日, 6月 23, 2010
金澤町家-2
先週に引き続き金澤町家について書こうと思います。
ひとくちに町家と言っても、町家系・武士系があります。
武士系とは、武家屋敷や足軽屋敷などの事です。
今回は、皆さんが馴染み深い町家系について書きます。
金澤町家は、藩政期から昭和25年頃までに建てられました。
町家系は、藩政期には主として商人や職人の店舗・作業場兼住宅として建てられたものですが、現在は店舗・作業場の用途がなくなり、住宅専用として使われています。
特徴としては、切妻平入りで、道路に面して隣家と軒を接するように敷地間口一杯に建っている点で、2階の階高も時代と共に高くなってきた。
藩政期には10尺建・12尺建の高さ制限があったようで、2間半建・3間建が建てられるようになったのは明治以降である。
町家系タイプとしては、
【平屋型】
平屋建で2階がない町家で、1階庇が付いていますが、大屋根との隙間がなく、大屋根の軒の出も浅いのが特徴です。
金沢では旧城下域の周辺部などに若干見られ、古いものが多く、中には石置き屋根の建物もあります。
【低町家】
表柱が2間(≒3.6m)強の建物で、軒先の高さは4.3m以下です。
金沢の伝統的な形の町家であり、明治期まで建てられていたが、それ以降はほとんど見られなくなった。
【中町家】
表柱が2間半(≒4.5m)強の建物で、軒先の高さは5.0m以下です。
2階の天井は何とか頭がつかえない程度の高さです。
【高町家】
表柱が3間(≒5.4m)以上の建物で、軒先の高さは5.0m以上です。
明治末以降、町家はどんどん高くなり、2階の天井も部屋として十分な高さになってきました。
このように、時代と共に2階の居室化の必要性が高まり、町家は高くなっていった。
町家の改修現場で、2階を部屋にするために低い町家を改造している痕跡を見ることがよくある。
皆さんも、注意深く市内を散策してみると、新しい発見があるかも…。
ひとくちに町家と言っても、町家系・武士系があります。
武士系とは、武家屋敷や足軽屋敷などの事です。
今回は、皆さんが馴染み深い町家系について書きます。
金澤町家は、藩政期から昭和25年頃までに建てられました。
町家系は、藩政期には主として商人や職人の店舗・作業場兼住宅として建てられたものですが、現在は店舗・作業場の用途がなくなり、住宅専用として使われています。
特徴としては、切妻平入りで、道路に面して隣家と軒を接するように敷地間口一杯に建っている点で、2階の階高も時代と共に高くなってきた。
藩政期には10尺建・12尺建の高さ制限があったようで、2間半建・3間建が建てられるようになったのは明治以降である。
町家系タイプとしては、
【平屋型】
平屋建で2階がない町家で、1階庇が付いていますが、大屋根との隙間がなく、大屋根の軒の出も浅いのが特徴です。
金沢では旧城下域の周辺部などに若干見られ、古いものが多く、中には石置き屋根の建物もあります。
【低町家】
表柱が2間(≒3.6m)強の建物で、軒先の高さは4.3m以下です。
金沢の伝統的な形の町家であり、明治期まで建てられていたが、それ以降はほとんど見られなくなった。
【中町家】
表柱が2間半(≒4.5m)強の建物で、軒先の高さは5.0m以下です。
2階の天井は何とか頭がつかえない程度の高さです。
【高町家】
表柱が3間(≒5.4m)以上の建物で、軒先の高さは5.0m以上です。
明治末以降、町家はどんどん高くなり、2階の天井も部屋として十分な高さになってきました。
このように、時代と共に2階の居室化の必要性が高まり、町家は高くなっていった。
町家の改修現場で、2階を部屋にするために低い町家を改造している痕跡を見ることがよくある。
皆さんも、注意深く市内を散策してみると、新しい発見があるかも…。
火曜日, 6月 22, 2010
町家表構え・格子編2
格子をもっと詳しく紹介していこうと思います。
社寺に扱われる格子に
碁盤(ごばん)格子・蔀(しとみ)格子・菱筬(ひしおさ)格子・透塀(すきへい)格子
があります。
社寺に前拝に嵌め込まれている格子が、碁盤格子です。
角材を碁盤目に組み合わせたもので、組子間は裏板は張らず、見透かしに
なっています。
蔀格子は、寝殿建築や社寺の周囲に使われ、碁盤目の格子戸で、
外締りや雨仕舞に使われ、裏板を張って、内側からは舞良戸となっています。
断面が菱型になっているのが菱筬格子です。廻廊の外窓に多く使われ、
内から外に視野が大きい特徴があります。
神垣を透き塀と称し、その腰に張られた板格子を透塀格子と呼びます。
お寺や神社に行ったときは、ちょっと気にして格子を見てみるのも面白いです。

にほんブログ村
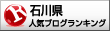
社寺に扱われる格子に
碁盤(ごばん)格子・蔀(しとみ)格子・菱筬(ひしおさ)格子・透塀(すきへい)格子
があります。
社寺に前拝に嵌め込まれている格子が、碁盤格子です。
角材を碁盤目に組み合わせたもので、組子間は裏板は張らず、見透かしに
なっています。
蔀格子は、寝殿建築や社寺の周囲に使われ、碁盤目の格子戸で、
外締りや雨仕舞に使われ、裏板を張って、内側からは舞良戸となっています。
断面が菱型になっているのが菱筬格子です。廻廊の外窓に多く使われ、
内から外に視野が大きい特徴があります。
神垣を透き塀と称し、その腰に張られた板格子を透塀格子と呼びます。
お寺や神社に行ったときは、ちょっと気にして格子を見てみるのも面白いです。
にほんブログ村
月曜日, 6月 21, 2010
LED照明
最近できたばかりのお店に行った。
健康食のビュッフェのお店だったけど、
お店の照明がすべてLED照明だった。
感激した☆
そのお店には『環境に配慮した電球、CO2削減』・・・
店舗で使用されやすい照明といったら白熱灯で、
消費電力は使用した時間だけ消費してしまう。
そのことを考えるとこのお店がすべての照明を
LED照明を使用したとなると、かなりのエコだぁ~!!!
ダウンライトのLED照明だったけど、お店の雰囲気も
暗くなく、十分すぎるほどの明るさだった★
1灯にLED7つほどはいっていてジぃーっと見ていると
目がやられるほど眩しかった。
照明に用いられるLEDであれば発熱もすくなく
これまた白熱灯とは違って照明から出される熱放射も
なく空調にもやさしい☆
LEDの威力恐るべし(◎o◎)
エコな空間で料理もおいしく最高だった。

にほんブログ村
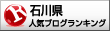
健康食のビュッフェのお店だったけど、
お店の照明がすべてLED照明だった。
感激した☆
そのお店には『環境に配慮した電球、CO2削減』・・・
店舗で使用されやすい照明といったら白熱灯で、
消費電力は使用した時間だけ消費してしまう。
そのことを考えるとこのお店がすべての照明を
LED照明を使用したとなると、かなりのエコだぁ~!!!
ダウンライトのLED照明だったけど、お店の雰囲気も
暗くなく、十分すぎるほどの明るさだった★
1灯にLED7つほどはいっていてジぃーっと見ていると
目がやられるほど眩しかった。
照明に用いられるLEDであれば発熱もすくなく
これまた白熱灯とは違って照明から出される熱放射も
なく空調にもやさしい☆
LEDの威力恐るべし(◎o◎)
エコな空間で料理もおいしく最高だった。
にほんブログ村
登録:
コメント (Atom)